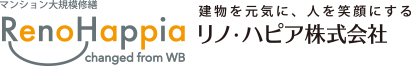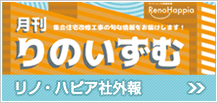Mabuhay! マニラのReno Happia BGCからです。
皆さん、他の国や土地に行くと、やはり気になるのはその土地の食事ではないでしょうか?
食には、その土地の文化がぎゅっと詰まっています。
また、他の人と食事をする時間を大切にしている国も多く、食事を共にするのは多くの国で歓迎の儀式でもあります。
そこには、各国のもてなしの文化も垣間見れます。
さて、フィリピン食というと、中々イメージするのは難しいと思います。
同じアジアでも、イメージの湧きやすい中華や韓国料理とは大きく違い、タイやインドなどのスパイスを沢山使う国の料理ともかなり違っています。
そのうえ、フィリピンは大小2000近くの島から成っており、地域によってその地域のカラーが食にも出てきます。
今はマニラに住んでいますが、それまではパラワン島という所で長く過ごしており、また、セブ島、ネグロス島、などにもよく行っていました。
その上で、フィリピンのローカルの食事に関して共通して言えるのは、味付けはかなり濃いめで甘い味付けと塩っぱいの料理が多く、辛い料理は結構苦手な人が多く、BBQなどは炭になるんじゃないかというくらい火を通し、刺身などの生ものはほぼ食べないという傾向があります。
これには理由があり、濃い味付けは少ないおかずで、沢山のご飯を食べる為で、過剰に火を通し、生のものは食べないのは、食中毒を恐れてのことです。
お米はどの地域でも価格が比較的安く安定して手に入り、簡単に満腹感を得られ、また医療費は法外なほど高いという経済的な理由に直結しているわけです。
そういった生活の経済事情が味付けや調理法に直結しているのです。
あと、甘くない飲み物は、水とビールぐらいです。
世界の色々な土地に行くほど、逆に日本食のコンセプトのユニークさは際立ちます。
素材そのものの良さ引き出し、出来るだけ手を加えずに薄目で繊細な味付けで、素材そのものの味や風味を最大限に引き出そうという、引き算の美学があります。
器や盛り付けにもそれは表現されていますね。
中華料理のように、素材はなんであっても大量の油と調味料で一定の同じ味にしたり、中東アジアの様にスパイスを大量に使って、辛味と香味でそもそもの素材の味など分からないといった足し算のコンセプトとは全く対極です。
昔読んだある作家のコラムで、日本食は食べる時にエネルギーを必要とせず、食と対決する必要がないので、鬱の辛い状態の時にでも食べることが出来たということが書いてあったのを思い出しました。
もちろん、どの土地にも美味しい料理があり、その土地の文化や事情と直結しており、ローカルの人達とローカルの料理を囲むのが、その土地の文化を理解するには一番手っ取り早い方法です。
普段オフィスや在宅で働いていると、食事というのは簡単に惰性で済ましがちですが、食は文化そのものと思って、楽しむ余裕があると、普段の日常も少し楽しくなるんじゃないでしょうか。
以上、今回は現地の食文化についてのご紹介でした!