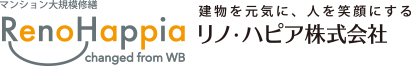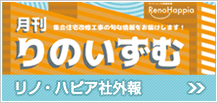ゴンドラSSPシステム
ブログ
こんにちは!本社工事部です。
現在施工している物件は、1階が立体駐車場の出入口および区民施設のエントランスホールとなっており、お住まいの方だけでなく多くの方が利用する建物です。
そのため、1階周辺の動線に大きな影響を与えないよう、仮設足場を組む方法ではなく「ゴンドラSSPシステム」を利用して外壁修繕工事を行っています。
〜ゴンドラSSPシステムとは〜
屋上の立上りコンクリートに専用フックを設置し、そこからワイヤーでゴンドラを吊り下げる工法です。
この方法により、歩道が狭くなったり、人や車両の出入りに制限がかかったりすることがありません。
また、飛散防止用のメッシュシートも全面に張ることができるため、仮設足場と同様に飛散防止対策をしっかり行うことが可能です。
【メリット】
・屋上からワイヤーで吊り下げるため、1階周辺を専有せずに施工ができます。
・メッシュシートと専用養生架台で囲むことで、塗料の飛散や資材の落下を防げます。
・組立や解体作業が短時間で済みます。
【デメリット】
・設置には大きな電気容量が必要となるため、建物に予備電源がない場合は発電機を設置する必要があります。
・ゴンドラでの作業となるため、足場を組んだ場合と比べると作業効率がやや下がります。